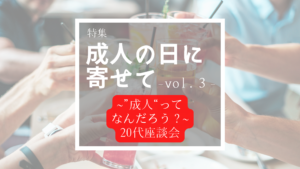「あえて自分で選ばない」ということ ~訪れるものに開かれる・実践編~
前回、「訪れるものに開かれる」というテーマで記事を書いていきました。おさらいすると、個々人の主体的な選択よりも世界から自らに降りかかってくるものを引き受けていく覚悟こそが重要だという構えが「訪れるものに開かれる」という言葉が意味するものでした。前回はこの言葉が持つ歴史的、思想的な背景からその意味について解説していきました。
前回記事の中で、「初めてこの言葉を聞いた時、自分がそれまで漠然と感じたり考えたりしていたことが一気に言語化されたような、そんな衝撃があった」と書きました。僕はこの言葉を知る以前から、日常的な場面の中で、「訪れるものに開かれる」というような構えが重要だと直感的に感じていたことが多くあったからです。
今回の記事は実践編です。もう少し具体的に、僕らの生活の中で「訪れるものに開かれる」という構えがどのようにして日常的な場面で意味を持ってくるのかについて、まずは「音楽を聴くこと」を事例に書いていきたいと思います。
探す遊びと浴びる遊び
「訪れるものに開かれる」という言葉を聞いて、まず最初に僕の好きなバンドの一つであるサカナクションの山口一郎さんの言葉を思い出しました。山口さんは「20代は、影響を受けるものを自分で決めない方がいい」ということを言っています。
山口さんによれば、今と昔とでは音楽を聞く体験の意味が変わっていっているそうです。昔は一つのアルバムを聞くのに数千円するレコードやCDを買う他ありませんでした。だからこそ音楽を聴く体験は特別で、一つのレコードやCDを大事に何度も聴き、深堀りして楽しむのが普通でした。山口さんはこれを「探す遊び」と表現しています。
一方で情報化が進んだ今の時代は、YouTubeやサブスクリプションサービスの普及によってほとんどお金をかけることもなく音楽を聴くことが出来るようになりました。その結果、膨大な情報、選択肢の中から、気に入ったものだけを選んで消費するようなスタイルへ音楽の楽しみ方が変化していきます。山口さんはこれを「浴びる遊び」と表現しています。
現代における日本の音楽シーンのトップランナーである山口さんは、現代の音楽シーンが「浴びる遊び」ばかりになってしまったと考え、かつてあった「探す遊び」の重要性を訴えています。
CDを1枚探すのも大変でした。3000円のアルバムをジャケ買いしたらハズレだった……といったようなこともよくありました。
そうやって手に入れたものを、もったいないから繰り返し聴く。難しいものにこそ何かあるはずだという期待感があったんですね。そうすると、そのうちに不思議と良さがわかってくる。そんな自分に対して高揚感が湧くんですよ(笑)。
僕は「探す遊び」を続けてきたから今の自分があると思っています。いまの20代を見ていると、「探す遊び」の方法を知らず、「浴びる遊び」をしている人が多いように見えます。ちょっと残念ですね。
Forbes JAPAN https://forbesjapan.com/articles/detail/22226/1/1/1
※太字は筆者
僕が10代の頃がちょうど音楽の視聴環境が、CDを購入する時代から、youtubeやサブスクリプションで聞く時代への過渡期であったと思います。そして、ここで言われている「探す遊び」という感覚は、20代の僕からしても、ギリギリまだ分かる感覚であるような気がします。確かに僕が中学生の頃くらいまでは音楽を聴くためにCD を買っていたし、数千円出して買ったCDなのだからと、何度も繰り返し聴いていました。買ったCDアルバムにどんな曲が入っていたかまでいまだによく覚えています。やっぱり最近聴いているアルバムよりもなんとなく特別である気がします。
また、音楽好きの僕の親戚のおじさんからも同じような話を聞きました。昔はCDやレコードが高かったから、レコードを買って家に持ち帰ってプレーヤーで聞くのは特別な体験だった。再生し始めたら、途中で飛ばしたり巻き戻したりは出来ず、アルバムをまるごと聞き通すしかなかった。今はタダ同然でたくさんの音楽が聴けるのはいいことかもしれないけど、音楽を聴くことが特別な体験ではなくなったとおじさんは話していました。
あえて自分で選ばない
こういった現象は高度な情報化がもたらしたもので、音楽に限らず様々な分野で起こっていることと言えるでしょう。映画館の椅子に長時間縛り付けられずとも映画を観ることができますし、リモートワークの普及によって場所や時間にとらわれずに仕事ができるようにもなりました。山口さんは利便性が向上し、無限の選択肢が与えられているこのような時代において、あえて自分で選ばないことの意義についてお話しされています。
今は簡単にさまざまな情報を手に入れられるけど、情報が多すぎて「自分で選んだもの」しか入ってこない。でも、あまりにも自分で選べる、決められる状況にいてはいけないんだなと思っています。
僕はメジャーデビューすることで、TVに出なくてはいけなかったり、10代の子たちの感情を研究したり、売れるためにはどうしたらいいかを考えたり、自分が本来思ってたことと全く違う研究をした。それをしなければならない状況に追い込まれた。
結果的にそれをしたことで、想像してない自分になれました。今では、自分にとって大きな財産になっています。
Forbes JAPAN https://forbesjapan.com/articles/detail/22226/1/1/1
確かに、最近になればなるほど、選べる選択肢が無限に増えていっている傾向はあると思いますが、一方で山口さんが言うような「自分で決めない」ということは、実は多くの人があえて言わずとも実践していることでもあると思います。例えば、月並みな例ですが、そこまで興味を持っていなくても友達が行きたい場所に一緒について行ったり、おすすめの本を読んだり映画を観たりということはよくあることでしょう。
しかし僕はこういうことがすこぶる苦手で、以前までは自分が本当に興味があったり、気が向いたりしない限りは、付き合いで人の誘いに乗っかることはありませんでした。しかし最近はこういった言葉に触れたこともあり、徐々に考え方が変わりつつあります。自分で決めないで人に任せてみる、自分は違うと思っていても、一回相手の提案に乗っかてみることを少しづつしていこうと思っています。他者に委ねることで、どんな世界に連れていかれるのか、これからが楽しみです。そしてこれは僕の中で「訪れるものに開かれる」という構えの実践篇であると捉えています。
おわりに
ということで今回は、「音楽を聴くこと」を皮切りに、「訪れるものに開かれる」という構えがどのようにして日常的な場面で応用できるのかについて書いていきました。自らの主体性を重視しないということは、ある意味では時代に逆行するような考え方ですし、なかなか受け入れがたい考え方かもしれません。前回の記事を読んだkikusukuの編集部からも「すぐには理解できなかった」という声もありました。正直自分でも自分の主体性はメチャクチャ大事だと思っています。ただ、自分が正しいと思っていることとは、反対のことに存在する価値を理解できることも一方で大事なことなのではないかなと思います。
kikusuku公式LINE、友だち募集中!
recommends‼

訪れるものに開かれる
ライター:あだち
「訪れるものに開かれる」
この言葉は僕の心をすっかり掴んでしまったパンチラインです。はじめにこの言葉を聞いた時、その意味を説明されずとも直感的に理解できるような、自分がそれまで漠然と感じたり考えたりしていたことが一気に言語化されたような、そんな衝撃がありました。「強い言葉」だなと感じました。なんか、意味はわからなくてもかっこいいでしょう?

「誰と」ともに生きるのか
ライター:あだち
「ともに生きる」。「ともに」って、一体誰を指しているんだろう。
家族や恋人、友人、学校のクラスメイトや職場の同僚、日常の中での人間関係を思い出してみる。日常的な人間関係の中で価値観が合わないと感じる瞬間はたくさんある。しかし、価値観の違う他者のことも尊重しなければいけない。これが難しい。時には誰かを守るために、他の誰かを悪く言わなければいけない時もある。複数の価値観や利害が衝突するような、そういう困難な状況に僕らは置かれている。

いつでもなにかが満たされていないわたしたちへ。
ライター:マモル
社会人になって、
最近、普遍的に人ってこうなんじゃないか?
と思うことがあります。
それは
「誰しもが今いる自分に満足できていない」
ということです。