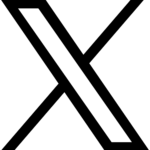演劇論から読み解く!ミュージカル『ミア・ファミリア』レビュー:日本初演・3LDK〈植原卓也×平間壮一×水田航生〉が熱演!
今回はミュージカル『ミア・ファミリア』のレビューをお届け。チケット即完・大盛況の内に東京公演の幕を閉じ、12月23・24日には大阪公演を控える本作について、演劇論を交えながらお伝えする。
『ミア・ファミリア』は、脚本・作詞をイ・ヒジュン、作曲をパク・ヒョンスクが務め、2013年に韓国で初演されてから何度も再演を重ねてきた人気ミュージカルだ。2020年には中国でも上演された本作が、2023年、遂に日本に上陸した。
日本版の演出を務めるのは、劇団ぼるぼっちょを主宰し、自らも俳優として活動する安倍康律。訳詞には、言わずと知れた名作詞家・詩人の森雪之丞。キャストには、ミュージカル等の舞台作品を中心に話題作への出演が続く人気俳優、植原卓也・平間壮一・水田航生が集結。三人は、ユニット『3LDK』としても活動しており、本作は満を持しての『3LDK』ミュージカル初共演となった。
なるほど、人生は「生き地獄」かもしれない。
黒いハットに黒いマント。人間ならざる存在にも思える「何か」=〈MC〉(演:植原卓也)は、舞台の幕開けと共に人間の昔話を歌い語り出す。
昔の昔、退屈した人間たちは、悪魔に「幸せになれ」と唆され、酒を飲み、歌を歌い、踊り、恋に落ちた。しかし、神は快楽に溺れる人間たちを「不幸になる」と諫めた。「生き地獄」になるのだと。
さて人間は、神と悪魔、どちらに従うべきであろうか。
MCの昔話に耳を傾けていると、私たちはいつの間にか1930年代のNY、リトル・イタリーのBar【アポロニア】へと辿り着いている。そこで働くボードビリアンのリチャード(演:平間壮一)は、客席を見つめた後、一人アポロニアについて話し出す。「今日が最後の舞台になる」と。合法カジノの建設を進めるマフィアによって辺り一帯が買い占められ、ここアポロニアも明日閉店することとなっていたのだ。
リチャードは、私たち観客に語りかけるように、若しくは舞台の練習をするかのように、いや、架空の観客へ向けて語り遊んでいるかのように、はたまた自分に問いかけるかのように話し、歌い踊る。そして、禁酒法により密造酒を販売するマフィアの懐が潤っていることを揶揄しながら、グラスを片手にこう苦悩するのだ。
「飲むべきか、飲まざるべきか!」(リチャード)
本作はコメディ要素も多く、笑って楽しめるエンターテイメント性の高いものであるが、作品を貫くテーマは切実なものだ。
「舞台という虚構の快楽に、溺れるべきか、溺れざるべきか!」
そう、酒を飲むか逡巡する彼のように。
ボードビリアンとしての誇りを持ち、パフォーマンスをすることが大好きなリチャードは「演じ、歌い、踊る」ことで生きてきたのだろう。現実の自分は、独り路上で育った過去を持ち、今は博打で借金まみれ。しかし、役を演じ、ボードビルの世界を生きている時だけは、現実の自分を忘れることができるのだ。
同じくボードビリアンのオスカー(演:水田航生)は、出会ったばかりのお嬢さま・ステラとの結婚を控えている。アポロニアが無くなるという事実から目を逸らすように、結婚準備に打ち込むオスカー。しかし、「結婚なんて幻想だ」とリチャードが言うように、熱い恋と結婚は別物。オスカーには、ステラがねだるティファニーのピアスを買うお金もないのだ。
一方、マフィアのスティーヴィー(演:植原卓也)には金がある。しかし、彼の現実も甘くはない。常に命の危険に晒され、いつ死ぬかも、自分が死んで悲しむ人がいるかも分からないのだ。そんな彼は、ボードビルの脚本を書き、生き生きと劇中の人物たちを演じてみせる。マフィアとして銃を突きつけ、借金を取り立てている様子より、ボードビルを演じている彼の方がよっぽど幸せそうに見えたのは、きっと筆者だけではないだろう。
そう、本作はアポロニアを舞台としながら、そこで上演されるボードビル『ブルックリン・ブリッジの伝説』『ミア・ファミリア』という二作品の稽古・上演が入り混じった構成が特徴的な作品だ。アポロニアに集うリチャードとオスカー、そしてスティーヴィーの三人は、劇と現実を行き来しているのである。
例えば、スティーヴィーは稽古でオスカーに突き飛ばされたり、顔を乱暴に掴まれたりしたことに怒り、天井へ拳銃を撃ち稽古をストップさせる。オスカーは『ブルックリン・ブリッジの伝説』で描かれる身分違いの恋に自分の結婚を重ね合わせるし、リチャードは借金相手のスティーヴィーに稽古で本物の拳銃を突きつけてしまう。
また、三つの世界を行き来しているのは彼らだけではない。観客もアポロニアに身を置きながら、いつの間にか『ブルックリン・ブリッジの伝説』の世界に引き込まれ、稽古が終わるとまたアポロニアに戻る。かと思えばアポロニアで『ミア・ファミリア』の稽古をしている様子を目撃し、更には、観客が生きる2023年の日本という現実を意識する瞬間もあるだろう。つまり観客は、時に劇中劇の世界へ没頭し、時にアポロニアでの物語へと没入し、気が付けば2023年に舞い戻る、その行き来を繰り返しているのだ。
この往来には、劇作家のブレヒトが提唱した手法の「異化効果」が見て取れる。異化効果とは、観客を登場人物に感情移入・同化させるのではなく、反対に同化を防ぎ、観客自らが思考することを促すような効果のことを指す。具体的には、演劇はフィクション・虚構であることを前提とした演出を行ったり、作品のテーマを予め明示したりすることによって、観客の能動的な鑑賞姿勢を生み出そうと試みるものだ(この説明はあくまで筆者が簡単にまとめたものなので、興味がある人は詳しく調べてみてほしい)。
本作が意図的に異化効果を用いていることは、MCの存在からも明らかであろう。MCは、作品冒頭の他、リチャードの内面が描かれるナンバーにて登場し、作品の最後を締めくくるのも彼のソロナンバーである。MCの存在は謎に包まれており、彼の存在する場所は【アポロニア】でも、劇中劇の世界でもないようである。〈MC〉という名前の通り、彼はこの舞台の進行役とも言える存在ではないだろうか。言わば、リチャードたちが生きるリトル・イタリーと客席を繋ぐような役割を担っているのだ。
MCが冒頭とラストで歌うのは、ブレヒト的な作品テーマの明示なのだろう。更に、中盤ではリチャードの心境やボードビル『ミア・ファミリア』について歌うことで、リチャードの孤独や悲しみ、葛藤を、ボードビル『ミア・ファミリア』の登場人物たちや、彼と似た苦しみを抱えた全ての人に通ずる感情に広げていくような効果を生んでいるのではないだろうか。リチャードの苦しみを彼一人のものにせず、同時に観客がリチャードに同化することも防いでいるのだ。
更に、本当のカーテンコールと錯覚するような劇中劇のカーテンコールがあったり、アポロニアでの物語が終幕した後にMCのソロナンバーが控えていたりする等、作品は緻密に現実と複数の劇世界を行き来するような工夫がなされている。観客はアポロニアにいる三人と共に、舞台の魔力に踊らされているのだ。
しかし、快楽とはすぐに消えゆくもので、現実は酒を飲み干すその瞬間の苦味のように喉を焼く。劇場に集う観客もまた、リチャードたちのように何か苦しい現実を抱えているかもしれない。舞台は幻想で、現実の問題を解決してくれるわけではないだろう。だが、人は一度知った快楽を簡単に手放すことなどできない。現実はあまりに苦いからこそ、人は酒を飲み、舞台を観て、恋に落ちるのだ。
ボードビル『ミア・ファミリア』の中で、マフィアのボスは麻薬に手を出すことを固く禁じている。しかしその一方で、現実のマフィアたちは密造酒を売り捌く。「合法」のカジノを建設する。
果たして何が「駄目」で、何が「良い」ことなのだろうか。快楽は人を「幸せ」にするのだろうか、それとも「不幸」にするのだろうか。
ボスは、三人の子どもたちに「サバイバル術」として三つの大切なものを教える。
「ファミリー、ナイフ、ミュージック!」
明るく繰り返されるこのフレーズが耳に残っている観客も少なくないだろう。ファミリーとは、共に生きる仲間のこと。ナイフとは、強く生き抜くための力。そしてミュージックは、人生を彩るような娯楽。
ファミリーという居場所を持ち、ナイフのような武器・身を守る強さを身につけ(「ズルくても勝てばいい」とMCは歌う)、ミュージックのように、娯楽で心を軽くする。この三つ、どれが欠けても、生きるのは苦しい。全て持っていたって、上手くいくことばかりではないのだから。生きていくためには、この三つ全てが必要不可欠なのだ。
娯楽は、ひと時の快楽かもしれない。現実の苦しみを無くすものではないかもしれない。
生きていくためには、現実の居場所も力も必要で、虚構だけではどうにもならないことばかりだ。
それでも、
リチャードのように「演じる」ことが、「役」が、自分の生きる居場所になることもある。
オスカーのように、虚構に触れることで自分の人生を見つめ直す人もいる。
スティーヴィーのように、娯楽のおかげで自分の生きる道を新しく見つけることもある。
そして私たちのように、大笑いをして、時に涙して、何かを考えて、リフレッシュして、明日を生きる活力をもらう観客がいる。
虚構だから、娯楽だからこそできることがあるのだ。
例えば、舞台は「伝説」になる力を持っている。
リチャードがアポロニア閉店に向けて『ブルックリン・ブリッジの物語』のタイトルを『ブルックリン・ブリッジの伝説』へと変えるように、オスカーは、リチャードに【アポロニア】の「伝説」を作ろうと訴えるように、人は「伝説」に焦がれている。いつの間にか忘れ去られていくものではなく、後の世に語り継がれていくもの=「伝説」に。
この現実世界で『ミア・ファミリア』が韓国から中国、日本と広がり続けていることも、一つの「伝説」であろう。そして、劇中でアポロニアが閉店を免れ、リチャードら三人の舞台は続いていくことも、やがて「伝説」になっていくのだ。その「伝説」はきっと、更にフィクションを交えて、人々を楽しませながら広がっていくだろう。
フィクションの内でも外でも、「伝説」は歌や踊り、酒と共に受け継がれていくのだ。
「人生に疲れた日はいつでも来ればいい 舞台に酔えば 幸せになれる」(MC)
舞台は、快楽は、必要なものか?
そんな問いが投げかけられた本作は、この一節が高らかに歌い上げられることで幕を下ろす。〈MC〉という存在もまた、その名の通り、舞台があるから生きられるものかもしれない。
苦しい時こそ、現実も快楽も全て飲み込み「酔って」しまえば良い。
この囁きは悪魔の声だろうか、神の啓示だろうか、はたまた人間の発見だろうか。
苦い現実を飲み干しながら、酒に恋に、舞台に酔う。ひと時の快楽に溺れ、また現実を生き抜く。その行き来は、まるで舞台を観る時のようではないか。
なるほど、虚実入り混じる生き様こそが、いつか「伝説」となるのかもしれない。
ミュージカル『ミア・ファミリア』
大阪公演 2023年12月23日(土)〜24日(日) 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
チケット情報他、公演詳細は公式HPをご確認ください。

kikusuku編集長のひなたです。演劇とテレビドラマと甘いものと寝ることが好き。立教大学大学院 現代心理学研究科・映像身体学専攻・博士前期課程修了。