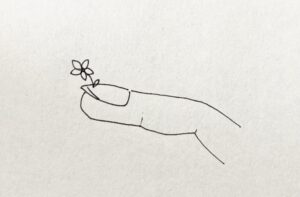「かたちを持たない私と、」#3
#3「記憶と、ともに」
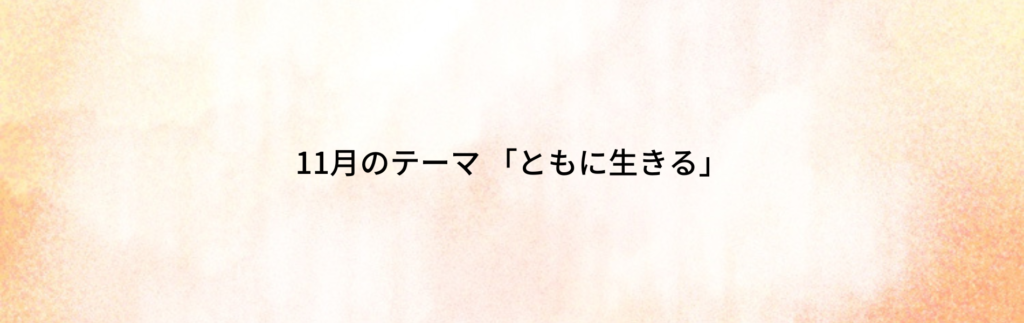
#2はこちら↓

kikusuku編集長のひなたです。演劇とテレビドラマと甘いものと寝ることが好き。立教大学大学院 現代心理学研究科・映像身体学専攻・博士前期課程修了。
「私は、あなたを知りません!!!」
ふと、必死な叫び声がフラッシュバックした。
「わたしは!あなたを!知りません!」
『……あ、はい。』
何かを訴えようと懸命に同じ言葉を繰り返す彼女の姿も、次第に思い起こされてくる。そうだ、これは数か月前に観た舞台のワンシーン。彼女は「本当のこと」を口に出せない病気(のようなもの)にかかっていて、彼女の目の前で「はい」と答えたのは、記憶を失くした男だった。男は、彼女の病気のことを知らない。
「私は、あなたを知りません」
彼女の悲痛な叫びが、耳の奥で脳内でこだまする。
***
もし記憶を失くしたら、私は何と、誰とともに生きるのだろうか。
私が何か/誰かと「ともに生きている」と感じる時、そこには必ず思い出が積み重なっている。
一緒に歩いた帰り道、劇場が暗転して静まり返ったその瞬間、初めて推しを目の前にした時の身体の震え、「美味しいね」と笑い合ったファミレスのボックス席、
この感覚たちは、どんな言葉にも写真にも映像にも残せない。この身体(からだ)が憶えているものたちだと思う。底がすり減ったお気に入りの靴も、無数の書き込みの跡が残る台本たちも、なんとなく捨てられないずっと前に使っていたスマホケースも、その「物」だけじゃ私に全てを教えてはくれない。

私の身体がここに在って、それを見て、それに触れて、感じることができるから特別になる。そんな、私の中に積み重ねてきたものたちは「記憶喪失」という事象一つで全て消えてしまうのだろうか。事故?認知症?アルツハイマー?
私と「ともに生きる」ものたちは、一瞬にして消えてしまうほど脆く儚いものなのだろうか。もし私が忘れてしまっても、覚えてくれている人はいるかもしれない。大事な「物」は、変わらずそこにあるかもしれない。それでも、私の中にある、私の中で「ともに生きている」記憶たちが消えてしまうとしたら、それはとても悲しい。
でも、その全てが完全に消えてしまうなんてこと、どこにもなくなってしまうなんてこと、その方が私には信じられないのだ。例え思い出せなくとも、「ある」んじゃないか。消えないんじゃないか。だって、私の身体を満たしているのは内臓でも血液でも水でも酸素でもなくて、「ともに生きる」誰かで、何かだ。
私をつくっているのは「ともに生きる」ものたちだと思う。それは記憶というよりむしろ「過去」の全てで、私が生きてきた道のりで、私が出会ってきた人で、物で、経験で、つまりは「私そのもの」じゃないか。

記憶はどこに存在しているのか――
ただ脳みそに保管されているだけのものだとしたら、私はこんなにも金木犀の香りを好きだと思わないだろうし、あの映画を観ながら頭から終わりまで涙を流し続けることもなかっただろう。きっと、身体が憶えているのだ。身体で憶えている。心で、憶えている。
姿かたちのないものは曖昧だけれど、かたちあるものより余程信じられるのはなぜだろう。
身体目一杯に詰め込んで尚溢れ出している記憶たちは、例え私が忘れようとも、私と「ともに生き続ける」のだと信じていたい。それは「過去」であり「今」であって、だからきっと「未来」でもある。
私は、信じていたいのだ。
「私はあなたを知りません」
そう叫び続ける、彼女のように。
#4へつづく
<#4は11月29日㈫公開予定です>
~Back Number「かたちを持たない私と、」~
#1「誰と、ともに」
#2「何と、ともに」