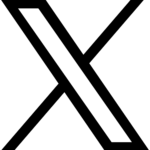香りに満ちる空洞で
「大好きな人たちを、大好きなまま、抱きしめていられますように」
到底“寂しさ”からは遠い書き出しかもしれないが、寂しさと愛情はいつだって表裏一体だ。
私が寂しさを自覚したのは一体いつからだろう。
それは物心つく前、思い出すこともできない頃から、きっと私は寂しさを知っていた。
まだ言葉を話せなかった頃、私はよく泣いて泣いて手のかかる子だったらしい。母は、ギャン泣きする私を常に抱っこしてあやしていたそうだ。ようやく泣き止んで眠ったと思ったら、ベビーベッドに置いた瞬間、またすぐに泣き始める猛獣っぷりだったとか(今の私を知っている人からすれば驚かれるかもしれない)。
「赤ちゃんが産まれた時に泣くのは何故だと思う?」
そんな問いかけをどこかで聞いたことがある。
産まれてきたことを喜ぶ嬉し涙なのか、否、産まれてきて“しまった”ことを嘆く悲しみの涙なのか、はたまた特に意味はないものなのか……。
私が産まれてきた時はどうだったのだろう。当時の記憶も、確かめる術もないけれど、たぶん「寂しさ」から来る涙だったのではないかと思う。
私はずっと「寂しさ」と共に生きてきた。そしておそらく、人は誰しも生まれた時から寂しさを抱えている。そんな気がしている。だって、人は誰でも涙を流したことがあるのだから。
だから私たちは、友をつくったり、恋をしたり、趣味に没頭したり、仕事を頑張ったり、夢を持ったりする。あちこちに愛を注ぐ。自分なりの「注ぎ先」を探す。
私の「寂しさ」はどこに行き着くのだろう。先の見えないトンネルのように鎮座する暗い空洞。しかし、その暗闇すら私は愛おしく思う。空洞を満たす“香り”たちを、私は抱きしめて生きていたいのだ。
香り。それは目に見えないけれど、確かに在るもの。そこに在って、私を刺激するもの。
空洞の中は真っ暗でも、例え何も見えなくとも、たくさんの貰いものがそこには仕舞われている。寂しさは、その寂しさの分だけ愛おしいものたちに出会わせてくれる。
「愛おしいものたちを、愛おしいまま、抱きしめていられますように」
これは、3ヶ月にわたる“寂しさ”についての思考、その記録。


kikusuku編集長のひなたです。演劇とテレビドラマと甘いものと寝ることが好き。立教大学大学院 現代心理学研究科・映像身体学専攻・博士前期課程修了。