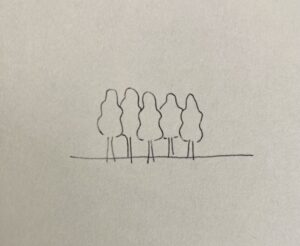横浜流星主演・清原果耶共演の映画『線は、僕を描く』感想レビュー!|水墨画に宿る<命>とは?
この記事を書いたのは……

kikusuku編集長のひなたです。演劇とテレビドラマと甘いものと寝ることが好き。立教大学大学院 現代心理学研究科・映像身体学専攻・博士前期課程修了。
あの時、彼は自分が泣いていることに気が付いていたのだろうか。
******
映画は、青山霜介(演:横浜流星)が椿の描かれた水墨画の前で立ち尽くし涙を流す場面から始まる。あの時彼は、自分の目から涙が溢れていること、そしてそれを自分が拭っていることに気が付いていたのだろうか。彼の腕は涙を拭いこそすれど、その心は完全に水墨画の方へと移っていたように思う。
あれは、霜介と<このもの>との出会いの瞬間だ。
<このもの>とは、言わば自分にとっての“唯一無二”。どうしようもなく特別なもの。
それは登山家にとっての”山”で、ギタリストにとっての”ギター”で”ロック”で、オタクにとっての”推し”で、節目節目で読み返したくなるような”あの本”でもある。
「“なる”んじゃなくて、変わっていくものなんじゃない?」
劇中で二度発せられるこの言葉の通り、霜介はこの水墨画との出会いをきっかけとして”変わって”いく。自分探しという言葉をよく耳にするが、何かに”なろう”とすることは時にたまらなく苦しいものだ。今・ここにいるありのままの自分をなおざりにして、実体のない理想像を求め続けるということだから。<このもの>との出会いは、気が付けば”変わっている”・”変わっていた”をもたらす、特別な出会いだ。
そうやって水墨画の世界へと導かれていく霜介。この水墨画、劇中では何度も<命>という言葉を使ってその出来が評価される。
「【水墨画】は筆先から生み出す「線」のみで描かれる芸術」(映画公式サイトより)
その線に<命>は宿っているのか、霜介や先輩の千瑛(演:清原果耶)らは、日々“自分の線”を探し続けている。
線に宿る“命”とはどのようなものだろうか。“自分の線”とは、一体何だろうか。
印象的だったのは、霜介や千瑛の師である水墨画の巨匠・湖山(演:三浦友和)の言葉だ。“自分の”花を描けないと悩む二人に対し、湖山は「その(花の)形の奥に何が見える?」と問いかける。
その花の奥には、壁や窓、あるいは家の雑貨などが見えているだろう。しかしもちろん、ここで言われる「奥に見えるもの」とは、これらの物を指しているわけではない。一見言葉と矛盾するようだが、「その形の奥に見えるもの」とは「目には見えないもの」ではないだろうか。
花の形を写し取ること(いわゆる模写に近いようなもの)つまり、どれほど「上手く」その花を再現できるかという部分に水墨画の本質はないのだと思う。その花が持つ美しさをありのまま伝えたいのなら、写真に撮ったり、その花を直接手渡したりする方が余程効果的だろう。

では、その花の本質は一体どこにあるのか。その形だろうか。その美しさだろうか。
何故その花を”水墨画”で描くのだろう。他のどの花でもなく、“この”花を描くのは何故だろう。何故、他の誰でもない”僕/私”が描くのだろう。
そこに生まれているのは<このもの>との出会いだ。
自分の目を、身体を通して見た”この”花の<命>。
”この”花を見たからこそ、自分の中に生まれた感覚/感情があるのではないか。
例え同じ花を見ていたとしても、花は見る人の数だけ違った姿をしている。ある人は花びらの鮮やかな赤色に目を奪われ、またある人は力強く伸びる茎に魅せられるかもしれない。その花びらを赤色だと感じる人もいれば、朱色だと受け取る人もいるだろう。

「僕/私にしか見ることのできない花」がそこにあり、その花を描こうとすることでしか生まれない水墨の線がある。それはきっと「僕/私にしか描けない線」であり、<命>を宿した線なのだ。
その花の本質を、美しさを、命を、表現したい。
自分の身体を通して出会った”この花”を表現したい。
その衝動こそ、水墨画に宿る<命>ではないか。
そして私は、そのような<命>の宿る作品のことを「表現」と「芸術」と呼びたい。
「芸術」とは、つくり手と<このもの>との出会い、そこに宿る<命>を描き出そうと挑み続けるものなのかもしれない。
******
水墨画、その線の奥には何が見えるのか。
それは、目には見えないもの。
それは描かれた物の<命>で、描き手の<命>だ。
真っ白な紙に、墨の美しい黒が生き生きと泳いでいく。その『線は、僕を描く』だろう。
【参考】
前田英樹・江川隆男(2016)『何を〈映像身体学〉と呼ぶのか』「立教映像身体学研究」 No.4。
江川隆男(2013)『超人の倫理---<哲学すること>入門』河出書房新社。
※<このもの>について、また「表現」について、映像身体学という哲学を基に記述しています。